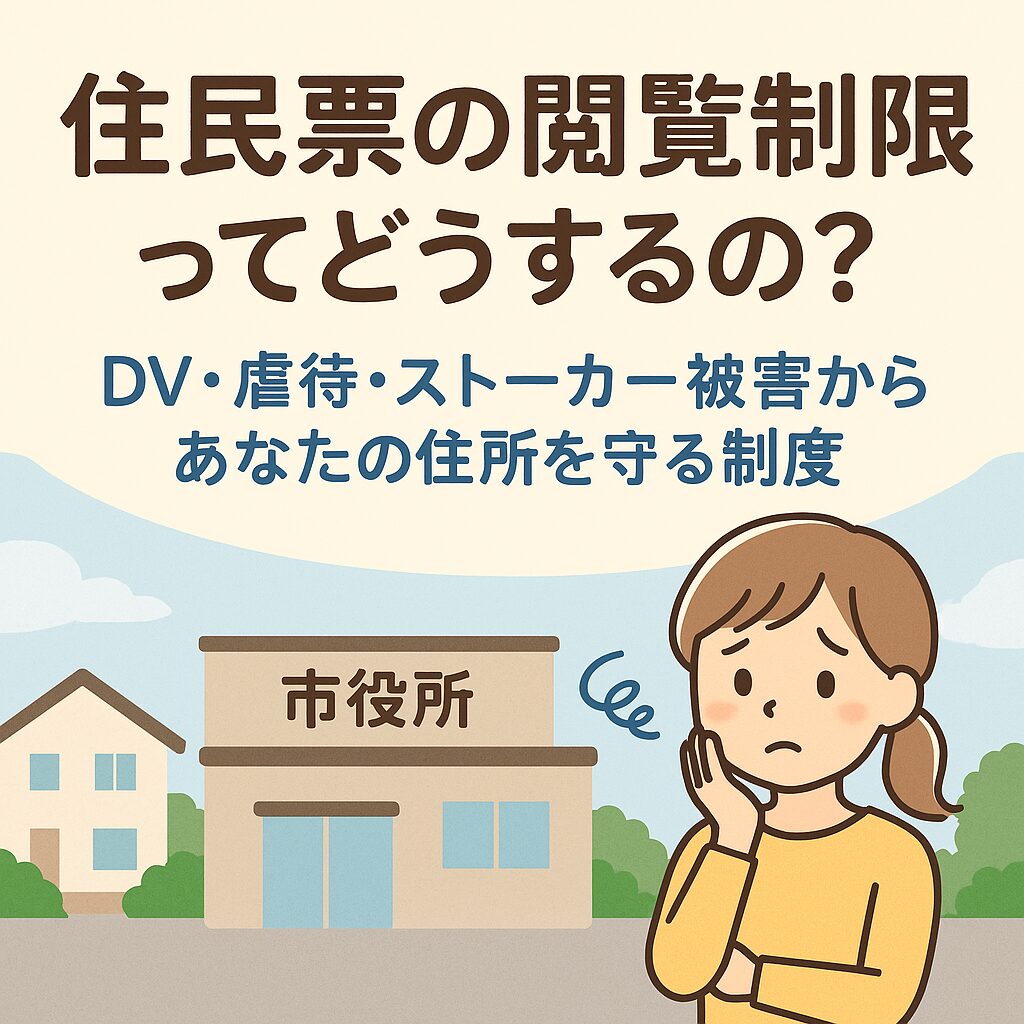こんにちは。
今回は、住民票の閲覧制限(支援措置)についてのお話です。
これは、DV(家庭内暴力)やストーカー、児童虐待などの被害を受けている人が、
住民票などから住所を特定されないように守るための制度です。
私自身も、幼い頃から親からの虐待を受けており、そこから逃れるためにこの措置を受けました。
この記事では私の実体験も交えながら、支援措置を受けるための流れや必要なことについて
わかりやすくお伝えしていきます。
住民票の閲覧制限とは?
住民票の閲覧制限(支援措置)とは、住民票や戸籍の附票を、
本人以外の人が取得したり閲覧したりできないように制限する制度のことです。
たとえば、DVをしている加害者(例:同一世帯の配偶者)が
「配偶者の住民票をください」と役所に行っても、交付されないようにしてくれます。
対象となるのはどんな人?
以下のような事情がある方が対象となります
- 配偶者や恋人からのDV・暴力を受けている人
- ストーカー行為の被害にあっている人
- 親からの虐待から逃げている子ども
- その他、住所を知られたくない特別な事情がある人(毒親で悩んでいる方等)
「少しでも心当たりがある」「誰かに住所を知られるのが怖い」と感じたら、
まずは一度、お住まいの役所や警察に相談してみることをおすすめします。
支援措置の手続きの流れ(私の場合)
※手続きの流れや必要書類は、自治体によって多少異なることがあります。
ここでは、私が実際に行った流れをご紹介します。
① 警察への相談(ここが重要です)
まず、現在の住所地を管轄する警察署へ相談に行きました。
その際に持参したのは
- 今まで受けてきた虐待を時系列でまとめた書類
- 「今後のお前の人生をめちゃくちゃにしてやる」と書かれた手紙
- 私に対する暴言が書かれたLINEのスクリーンショットを印刷したもの。
特にこの手紙が有効でした。「今後、危害が及ぶ可能性がある」と判断してもらえたからです。
どんな些細なものでも構いません。証拠はできるだけ用意しておくことをおすすめします。
② 住んでいる市区町村の役所へ行く
役所に出向いて「住民票の閲覧制限を申請したい」と伝えると、
簡単な聞き取りの後、必要な申出書などを渡されました。
③ 申出書の記入と本人確認書類の提出
その場で申出書を記入し、運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認を行います。
④ 審査 → 制限スタート
役所による審査を経て、「支援が必要」と判断されれば、
住民票などの閲覧制限が正式に適用されます。
閲覧制限の対象となる書類
- 住民票(除票を含む)
住民票の除票とは、転出や死亡などにより削除された住民票の記録のことです。
過去に住んでいた住所の証明や死亡の確認に使われます。 - 戸籍の附票(除票を含む)
その戸籍が作られてからの住所の履歴が記録された書類です。
※ 注意点
閲覧制限では、戸籍謄本や戸籍抄本は制限できません。
それらには現住所ではなく本籍地が記載されているため、対象外となります。
そのため、本籍地は現住所と離れた場所にしておいた方がよいです。
注意しておきたいこと
- 閲覧制限の有効期間は原則1年間です。継続したい場合は、更新手続きが必要です。
(更新の書類が毎年役所から送付されます) - 裁判所の命令や正当な理由がある場合には、慎重な審査の上で開示されることもあります。
※たとえば、何か犯罪を犯した場合は当然ですが開示されます。 - 自治体によって必要書類や対応が異なることがあります。
まずは、お住まいの市区町村に確認してみてください。
最後に
この制度は、人の安全な暮らしを守るための仕組みです。
私自身、この制度に救われた一人です。
「住所を知られないようにしたい」「人生を変えたい」
そう思っている方の、小さな勇気につながれば嬉しいです。