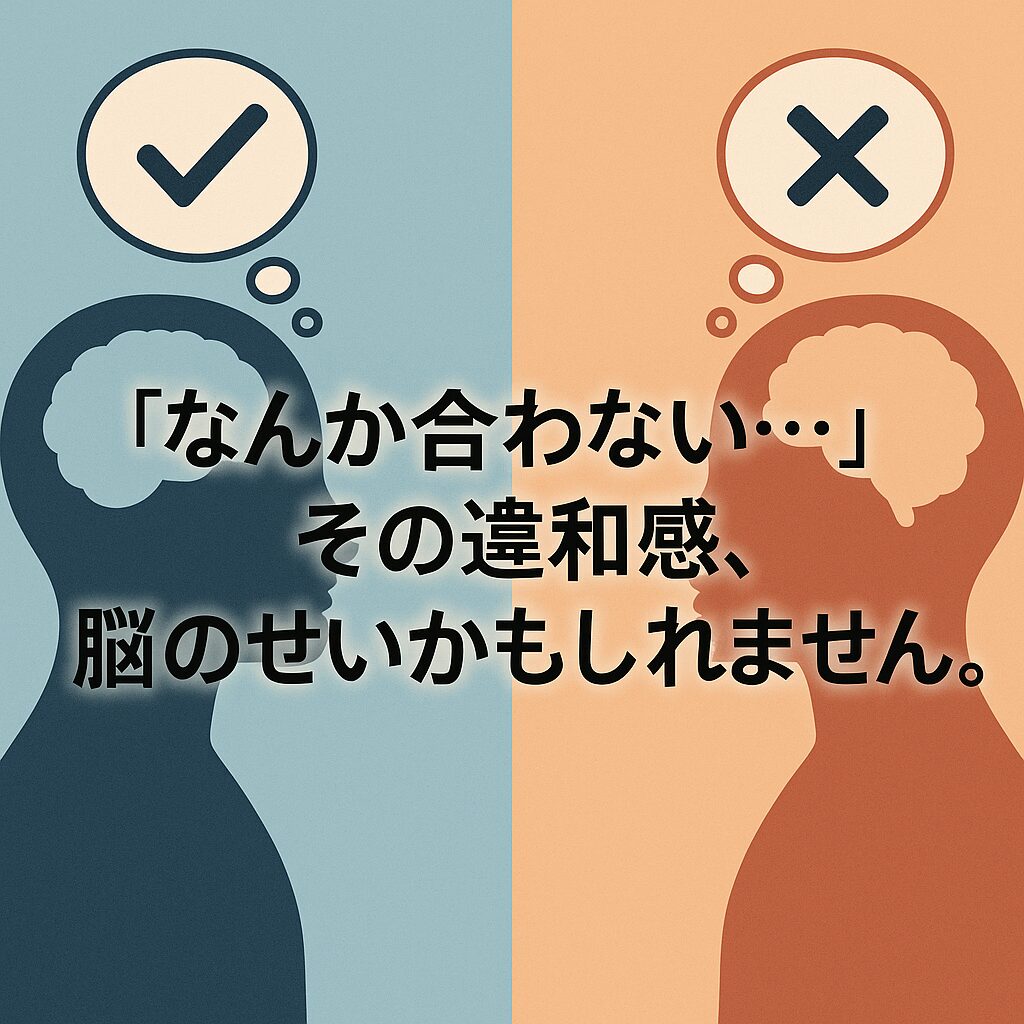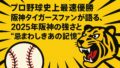「この人とは合う気がする」
「この人とは話がかみ合わないなあ・・・」
人と関わっていると、こう感じること、ありませんか?
これって、なにが違うんでしょうか?
今日はそんな「合う/合わないの違い」について、考えていきたいと思います。
「なんか合わない…」その正体は“脳の感じ方”
人に対する“感じ方”って相手によって違いますよね?
たとえば――
- ある人との「沈黙」は“落ち着く”
- 別の人との「沈黙」“気まずい”
これって、実は「脳」が原因なんです。
その人に対して脳がどう感じるか、ということ。
その人の”会話のテンポ”や”物事への反応”や”立ち姿”とか、
こういったことに「違和感」を覚えることによって、
人は「なんかこいつと合わへんな」って感じるようになるんです。
脳が求めているのは「予測できるという安心」
人の脳って、「予測できること」に対して安心するんだそうです。
- 自分と同じ会話のテンポ
- 自分と同じ考え方
- 共通の“ノリ”
そういうものがあると、「この人、安心するなあ」ってなる。
「安全=合う」ってことですね。
だから逆に自分の予想と違う反応や間の取り方をされると、
脳は警戒モードに入ってしまう。
これが、「合う/合わない」の原因なんです。
「なぜ違うか」を知ってるだけで楽になる
だから、合わないと感じる相手がいても、
「自分が未熟だからだ」とか「もっと努力しなきゃ」とか、
責めなくていいと思います。
ただ脳の仕組みの問題なんです。
合う人・合わない人がいるのは当たり前。
人間がそういう仕組みになっているんだから。
警戒してしまっているんです。
でも、「なぜそうなるのか?」を知ってるだけで、
少し気持ちを楽にするきっかけにできると思うんです。
「合わない」ことで分かり合えないのは辛いことです。
「なぜそんな考え方をするんだろう?」
「ありえない」
「あいつは最低のヤツだ」
そう考えて、相手を受け入れたくなくなるのも当然だと思います。
だって感覚が違うんだもの。
でも、そうすると自分の心がどんどんすり減ってしまいます。
「脳の仕組みだから、合わないのも仕方ないよね」
「仕方ないか」と思えるだけで、
少しだけ妥協してみようかな、歩み寄ってみようかな、
って気持ちになれるかもしれません。
そうしたら、日々の人間関係も少し、良い方へ向かっていけるんじゃないでしょうか?